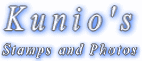花の写真|蓮(ハス、Lotus)と睡蓮(スイレン、WaterLily) |
ページ内索引 [ 蓮の花|蓮の蕾|睡蓮 ] 関連:世界の水辺に咲き・可憐に咲く花の切手
蓮の花
ハス(蓮、学名:Nelumbo nucifera)は、インド原産のハス科多年性水生植物。
蓮(ハス)と睡蓮(スイレン)の違い(草津市立水生植物公園より転載)
蓮と睡蓮は両方とも抽水(ちゅうすい)植物といって、水の底の土や泥に根を張り、水面(水上)に葉と花を展開します。一部の品種では例外もあるようですが、一般的には次のような違いがあります。
|
ハス |
スイレン |
|
|
花の特徴 |
水面から高く咲く。 |
水面近くに浮かぶように咲く。熱帯スイレンは、水上で咲く。 |
|
葉の特徴 |
撥水性があり、光沢がない。 |
撥水性がなく、光沢がある。 |
|
根の特徴 |
成長期は、細い地下茎がぐんぐん伸びるが秋には先端が肥大し、これがレンコンになる。 |
種類が多いため、様々であるが、耐寒性スイレンは、ワサビのように太い。地下茎が、ゆっくり成長していく。 |
参考 : 切手|水辺の花 古代蓮の里では、行田蓮を含む42種類の花蓮 京都の石田精華園
|
ご注意)画像の無断転用はお断りします。 |
■ハスに関しての逸話 : 当麻曼荼羅と中将姫
当麻曼荼羅(たいま まんだら)とは、奈良の当麻寺に伝わる中将姫伝説のある蓮糸曼荼羅と言われる根本曼荼羅の図像に基づいて作られた浄土曼荼羅の総称である。当麻曼荼羅の原本については、中将姫という女性が蓮の糸を用い、一夜で織り上げたという伝説がある。
曼荼羅という用語を用いているが、密教の胎蔵界・金剛界の両界曼荼羅とは無関係である。浄土曼荼羅という呼称は密教の図像名を借りた俗称であり、現代における正式名称は、浄土変相図である。中将姫織成の伝説のある根本曼荼羅の原本も、近年の調査の結果、伝説のような蓮糸を織ったものではなく、錦の綴織りであることが判明している。
|
綺麗な蓮の花 この世のものとは想像が出来ない |
|
 |
 |
|
綺麗な蓮の花 微妙な色合い、大きな花弁 4日の命です |
|
 |
 |
中将姫 ・・ 今は昔、藤原鎌足の子孫である藤原豊成には美しい姫があった。後に中将姫と呼ばれるようになる、この美しく聡明な姫は、幼い時に実の母を亡くし、意地悪な継母に育てられた。中将姫はこの継母から執拗ないじめを受け、ついには無実の罪で殺されかける。ところが、姫の殺害を命じられていた藤原豊成家の従者は、極楽往生を願い一心に読経する姫の姿を見て、どうしても刀を振り下ろすことができず、姫を「ひばり山」というところに置き去りにしてきた。その後、改心した父・豊成と再会した中将姫はいったんは都に戻るものの、やがて當麻寺で出家し、ひたすら極楽往生を願うのであった。姫が五色の蓮糸を用い、一夜にして織り上げたのが、名高い「当麻曼荼羅」である。姫が蓮の茎から取った糸を井戸に浸すと、たちまち五色に染め上がった。當麻寺の近くの石光寺に残る「染の井」がその井戸である。姫が29歳の時、生身の阿弥陀仏と二十五菩薩が現れ、姫は西方極楽浄土へと旅立ったのであった。
蓮の蕾(つぼみ)
果実の若芽は、果実の中心部から取り出して、茶外茶として飲用に使われる。ハスを国花としているベトナムでは、雄しべで茶葉に香り付けしたものを花茶の一種であるハス茶として飲用する。
三重県 名張・青蓮寺 伊賀・慶明寺で撮影。
|
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
 |
 |
|
■橿原市高殿町 藤原宮跡の大極殿跡南東方向にあるハス池には、唐招提寺蓮・大賀蓮など、11種類が植栽されています。 |
|
|
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
 |
 |
 |
|
|
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
 |
 |
|
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
 |
 |
|
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
蓮の蕾(ハスの花のつぼみ) |
 |
 |
はすの実と呼ばれる果実(種子)にもでん粉が豊富であり、甘納豆や汁粉などとして可食である。中国や台湾では餡にして、月餅、最中などの菓子に加工されることも多い。餡にする場合苦味のある芯の部分は取り除くことが
多いが、取り除いた芯の部分を集め蓮芯茶として飲まれることもある。 また、蓮肉(れんにく)という生薬として、鎮静、滋養強壮作用があります。
睡蓮(スイレン)
行基さんのお寺・奈良県・西大寺の喜光寺の睡蓮を中心に。名張市内、インドネシア・バリ島、USA・NY州にて撮影。
スイレン属(スイレンぞく、学名:Nymphaea)は、スイレン科の属の一つで、水生多年草。単にスイレン(睡蓮)と呼ぶことが多い。 日本にはヒツジグサ(未草)の1種類のみ自生する。日本全国の池や沼に広く分布しています。 白い花を午後、未の刻ごろに咲かせる事からその名が付いたと言われる。
睡蓮を産地で大まかに分けると、熱帯産と温帯産に分けられる。園芸ルートで一般的な物は温帯産、アクアリウムルートで一般的なものは熱帯産。
温帯産は水面のすぐ上に花を付けるが、熱帯産は水面から高く突き出た茎の先端に花をつけるので、区別は容易です。
熱帯スイレンと呼ばれるものは、原産地はエジプトとされ、熱帯から亜熱帯にかけて約40種が分布し、交配によって多数の園芸種が存在する。印象派の画家クロード・モネの大作「睡蓮」も有名。
Good morning. This morning of the Kii Peninsula is cloudy. Very cold in spite of the summer. As if in response to,...
Posted by 楽しい切手収集と旅行写真 on 2015年6月29日
※青蓮寺は名張駅の南方にあり、周囲は小高い山々に恵まれている。室町時代、青木信定がこの地に青蓮寺城を開城したが、天正9年、織田信長の軍勢により落城した。世にいう“天正伊賀の乱”である。当寺はその城址に建てられ、現住職の耕野一仁さんは18世である。近くに青蓮寺湖があり、ダムとして利用されている。“青蓮(しょうれん)”は花の名前で“青蓮華(しょうれんげ)”ともいう。葉は長く広く、鮮やかな青色をしていることから、仏の眼にも例えられるが、その昔、弘法大師がこの地で「青い蓮が咲き開く夢を見た」ということに由来する。
|
※誤りがあった場合は気付いた時に修正していますので、誤表記を発見された方はぜひ教えてください。 Wikipediaを参考にさせていただいております。 |
||
|
花の写真|蓮(ハス、Lotus)と睡蓮(スイレン、WaterLily) |
|
|
花と果実の写真の索引 [ 蓮と睡蓮|春の花と果実[ No.1|No.2 ]|夏の花と果実[ No.1|No.2 ]|秋の花と果実[ No.1|No.2 ]|冬の花と果実|四季咲き・温室の花 ]