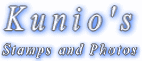京都市写真集|左京区の南禅寺と国宝・琵琶湖疎水施設 |
はじめに
このページでは仕事の関係で京都市内(烏丸三条、百万遍他)に10年間生活し、気が付けば何の写真も残っていないので、京都の風景を改めて撮り直した。
2025年5月16日 新たに国宝に指定されるのは、びわ湖から京都へ水を運ぶ長大な運河を構成する「琵琶湖疏水施設」です。 京都市の南禅寺の境内を横切るれんが造りのアーチ型の水路橋をはじめ、山を貫くトンネルや、舟を運ぶ鉄路の合わせて5つの施設で構成されています。
ご注意)画像の無断転用はお断りします。
南禅寺
■南禅寺(なんぜんじ)は、京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗南禅寺派の大本山の寺院。山号は瑞龍山。本尊は釈迦如来。開山は無関普門(大明国師)。開基は亀山法皇。正式には太平興国南禅禅寺(たいへいこうこくなんぜんぜんじ)と号する。日本最初の勅願禅寺であり、室町時代に定められた五山十刹の制において京都五山および鎌倉五山の上に置かれる「五山の上」の寺院とされ、日本の全ての臨済宗の寺院の中で最も高い格式を持つ。
弘安10年(1287年)に「上の御所」に亀山上皇が持仏堂を建立し「南禅院」と名付けた。
★藤堂 高虎(とうどう たかとら)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。伊予今治藩主、後に伊勢津藩の初代藩主となる。津藩藤堂家(藤堂家宗家)初代。
藤堂高虎は、黒田孝高、加藤清正と並び、「築城三名人」の一人と称される。数多くの築城の縄張りを担当し、層塔式天守を考案。高石垣の技術をはじめ、石垣上には多聞櫓を巡らす築城の巧みさは、その第一人者といっても過言ではない。また外様大名でありながら徳川家康の側近として幕閣にも匹敵する実力を持つ、異能の武将であったといえる。
琵琶湖疎水施設
■琵琶湖疏水(びわこそすい)は、京都への通船、水力発電、飲料水の供給など多様な目的で計画された、明治期の画期的な土木工事。
観音寺の取水口から京都蹴上までの延長11kmに及ぶ。工事は田辺朔郎を主任に、1885年(明治18)から1890年(同23)に及んだ。 公益社団法人びわ湖大津観光協会
 |
||
★疏水は、琵琶湖から京都市内に向けて引かれた水路である。滋賀県大津市で取水され、南禅寺横を通り京都市東山区蹴上迄の区間である。疏水の工事は1885年に始まり、1890年に竣工した。
疏水の目的は大阪湾と琵琶湖間の通船や水車動力による紡績業,潅漑用水,防火用水などであった。ところが水力発電の有利性が注目されるようになり、1889年に蹴上に発電所が建設され,91年には送電を開始した。 (南禅寺より)
Lake Biwa Canal (琵琶湖疏水 or 琵琶湖疎水, Biwako Sosui) is a historic waterway in Japan connecting Lake Biwa to the nearby City of Kyoto. Constructed during the Meiji Period the canal was originally designed for the transportation of lake water for drinking, irrigation and industrial purposes, but also provided for the conveyance of waterborne freight and passenger traffic. From 1895 water from the canal supported Japan's first hydroelectric power facility, providing electricity for industry, street lighting and Kyoto's tram system. In 1996 the canal was recognized as a nationally designated Historic Site.
注)Wikipedia、南禅寺と公益社団法人びわ湖大津観光協会のHP等を参考にさせてもらっています。
|
京都市写真集|左京区の南禅寺と琵琶湖疎水施設 |
|
|